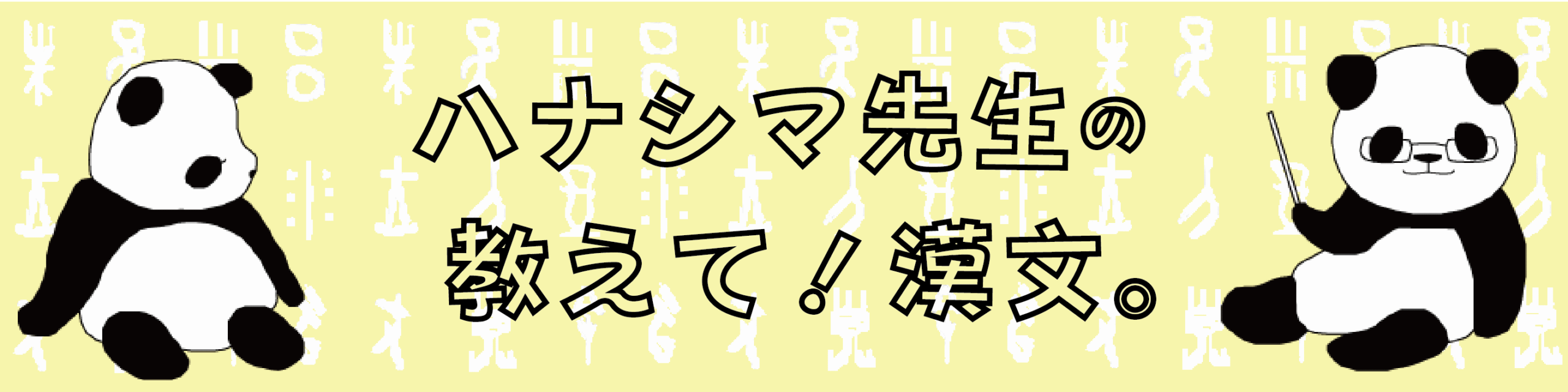みなさんこんにちは!このページでは、中国の伝統的な恋愛・結婚・性愛にまつわるクイズを紹介します。ぜひ楽しみながら中国文化を味わってみましょう!
もくじ
『詩経』(しきょう)とは、中国最古の詩集で、恋愛の詩が多く収録されています。
【Q1】
『詩経』の恋愛詩は、しばしば儒教(じゅきょう)的に無理やり解釈されることがあります。
下の「狡童(こうどう)」という作品は、どのように解釈されているのか、
次の選択肢から選んで下さい。
A:従順ではない妻を強く責める内容
B:君主が他の臣下とばかり政治の話をしているのを嫉妬する内容
C:自分の子どもが言うことを聴かずに困り果てている内容
有女同車
【現代語訳】
あのずるい人、私に口もきいてくれない。
あんたのせいで、ご飯ものどを通らない。
あのずるい人 私と仲良くしてくれない。
あんたのせいで 眠れもしない。
【書き下し】
彼の狡童 我と言わず
維れ子の故に 我をして能く餐らわざらしむ
彼の狡童 我と食わず
維れ子の故に 我をして能く息わざらしむ
参照:牧角悦子『詩経・楚辞』(角川ソフィア文庫、2012年)
【Q1正解】
B
では、実際にはどのように解釈されてされたのでしょうか?以下の現代語訳をご覧ください!
あの頭の悪い殿さまの子は賢者である私と仕事をしないで
(勝手なやつらの言いなりなったせいで追放されてしまった)
お前のせいで私たちは憂いでご飯も食べられない。
あの頭の悪い公子は賢者である私に相談することもなく
(勝手な奴らの言いなりなったせいで追放されてしまった)
お前のせいで私たちは憂いで休むこともできない。
(参照:牧角悦子『詩経・楚辞』(角川ソフィア文庫、2012年))
若い女の子?のいじらしい恋心を表現した歌
→オッサンがバカな殿さまの子どもへの心配を表現した歌
に解釈されているのは面白いですね笑
『論語』(ろんご)の「子曰く(しいわく)」で有名な孔子は、実は恋愛に関する詩にコメントを残しています。Q2はそのコメントにまつわる問題です。
【Q2】
『論語』の中で孔子が下の詩に対して行ったコメントとして正しいのはどれでしょう?
A:「遠距離恋愛は辛い」と読み手に同情する。
B:ニワザクラが「君」のことを指していて、
「君」へのいとおしさを表していると解釈する。
C:「実は読み手はそこまで「君」が好きでは
ない」と予想する。
D:「実は読み手は遠距離以外に特別な理由が
あって行けない」と予想する。
【詩の現代語訳】
ニワザクラの花はひらひらと揺れている。
君のことを想ってはいるけれど、
家が遠くてなかなか会いに行けないのだ。
【Q2正解】
C
この読み手が想い人のことが本当に好きだったら、家の遠さとか関係なく会いに行くと思うので、孔子のコメントは合っていると思います。意外と孔子って恋愛マスターだったのかも?笑
中国では多くの詩が作られましたが、男女の恋愛・結婚にまつわる詩も多く存在します。
【Q3】
中国では、伝統的にポピュラーな男女関係の詩のジャンルがいくつか存在します。
その内容に当てはまるものを以下から1つ選んで下さい。
A:女性がダメな男性と結婚した後悔を述べる詩
B:男性の別れた妻への未練を表現した詩
C:妻が1人で不在の夫を寂しく待つ詩
D:男女の付き合う(結婚する)前の甘酸っぱい恋心を描いた詩
現代の歌だとどれもありそうですが、いかがでしょうか?
【Q3正解】
C
【Q3解説】
A→古くは「氓(ぼう)」などが存在するが、ポピュラーではない。
B→夫に捨てられた妻の嘆きを描いた作品(例:魚玄機「寄李億員外(李億員外に寄す)」)や、
死別した妻への気持ちを表現した作品(例:潘岳(はんがく)の「悼亡詩(とうぼうし)」や梅尭臣(ばいぎょうしん)の「悼亡詩」)は多い。
C→「閨怨詩(けいえんし)」というジャンルが存在し、 王昌齢(おうしょうれい)の「閨怨」など、多くの作品がよく作られた。
D→古くは「子衿(しきん)」などが存在するが、その後定番とはならなかった。理由としては、
伝統的な中国の結婚スタイルはお見合い(=家同士の付き合い)なので、そもそも恋愛結婚は非常にまれだったことが大きい。
Q1に続き、Q4も恋愛結婚への儒教(じゅきょう)の影響に関する質問です!
【Q4】
中国では、古くから「儒教的な理想の妻のあり方」というものが存在していました。
このあり方を表した行動ではない選択肢を1つ選んで下さい。
A:夫が亡くなったら、自分も速やかに後を追うべき。
B:夫が亡くなったら、息子を夫の代わりとして従うべき。
C:夫の行うことには口を出さずに従順であるべき。
D:夫が先に亡くなった際、子どもがいれば再婚してでも育て上げるべき。
現代の価値観で考えると、かなり過激な選択肢が多いですが、どれが間違っていると思いますか?
【Q4正解】
D
【Q4解説】
・A→「未亡人」=(夫が亡くなっているのに、後を追って死んでいない妻)の原義から理解できる。
・B→中国には伝統的に女性は「三従」(未婚の時は父に、結婚してからは夫に、夫が亡くなってからは息子にそれぞれ従う)を行うべきという価値観が存在していた。
・C→厳密に言えば「夫に従順でありつつ、夫に的確なアドバイスをして支える」という無茶ぶりが理想とされることも多かった。
・D→『後漢書』列女伝などで、再婚を拒んで自殺した人が「列女」として賞賛されることがあったことから、おかしいことが分かる。ただ、実際には再婚する女性も多かったので、再婚を拒否する=絶対ではなかった。
儒教の教えは現代から見ると男尊女卑だと感じる可能性が高いので、女性はなかなか不快に思われるかもしれません…
ただ、A・B・Cを当時の全ての女性が実際に行った訳ではないのは注意点です。
例えば、Q7で取り上げるように、夫(皇帝)にコントロールされずにふるまうケースも散見されます。
次は古い時代の中国の結婚にまつわる習慣・取り決めに関する問題です。
【Q5】
古代中国における婚姻にまつわる内容について、最も適切ではない選択肢を1つ選んで下さい。
A:婚姻にかかる費用としては、結納金(ゆいのうきん)より披露宴(ひろうえん)のほうが倍以上かかることが一般的であった。
B:結婚しない者には多く課税されることがあった。
C:一般的には男性は30歳まで、女性は20歳までが結婚適齢期とされた。
D:結婚するタイミングで女性の生年月日を教えてもらい、良い占い結果になったら実際に結婚する。
※結納金=結婚する際に男性側から女性側へ贈られる、結婚の準備金。
【Q5正解】
A
【Q5解説】
・A→庶民の場合、結納金が1万銭~、披露宴代が5000銭ほどで、結納金のほうが高い。
→占い1回で数十~数百銭なので、現代日本の感覚だと披露宴代=50万程度、結納金=100万程度か。
Bについては、いわゆる独身税のようなものが存在している時期があったということです。
Cについては、昔なのでもっと低いイメージがありますが、意外と高いですね💡
Dについては、結婚を含め、当時は旅行や土木工事など、あらゆる物事について占いをしていました。
【Q6】
・古代中国での離婚にまつわる内容について、正しい選択肢を1つ選んで下さい。
A:夫が妻と離婚できる条件として、「妻が嫉妬深い」というものがあった。
B:離婚をするためには、現代と同じようにどちらか1人が書類を提出すれば受理された。
C:女性から離婚を切り出すことはできなかった。
D:「離婚」という言葉は、秦の始皇帝(しこうてい)の時代からすでに確認できる。
【Q6正解】
A
【Q6解説】
A:嫉妬の他、離婚できる条件として「子どもができない」「義両親に従順でない」
などが挙げられるが、このあたりは儒教の影響が強そう。
(ただし、実際に嫉妬が理由で離婚した例は見られない。)
B:当時離婚するためには、2人が役所に行って申請する必要があった。
C:少例だが女性から離婚を切り出すケースがある。
D:「離婚」という熟語は魏晋南北朝時代が初出。
女性の嫉妬が原因で離婚できるというのは、意外かもしれません。中国では伝統的に男性が妾(めかけ=妻以外の愛人)を持つことができたため、嫉妬する女性は多かったのかも?
Q7:中国における妻の嫉妬エピソードとして誤っているものを1つ選んで下さい。
A:前漢時代の劉邦(りゅうほう)の妻は、夫の死後、夫が寵愛していた妾の手足を切り落とした。
B:隋の文帝(ぶんてい)の妻は、夫が後宮を持つのを嫌がり、夫がこっそりと妾を作ると、その妾を殺した。
C:唐の宜城公主(ぎじょうこうしゅ)は、夫に妾ができたことに怒り、妾の耳や鼻や夫の髪を切った。
D:北宋の趙匡胤(ちょうきょういん)の妻は、夫が侍女の美しい手を誉めた時、その手を切り取って盆に盛り夫に捧げた。
【Q7正解】
D
【Q7解説】
A→呂太后(りょたいこう)という人物で、中国三大悪女の1人。
B→独孤伽羅(どっこから)という人物で、とても賢い人物であった。(なお嫉妬)
D→手を切り取ったのは南宋の光宗の妻=李鳳娘(りほうじょう)で、「黒い鳳凰」という異名を持つ。
建前では儒教の教えで「妻は夫に従順であるべし」とされつつも、この教えと真逆のエピソードが散見されるのが面白いですね。今も昔も女の嫉妬は恐ろしい…
の、Bの文帝は、奥さんに振り回されすぎて、「私は皇帝になったのに全然自由がない…」とグチったことがあるそうです💦皇帝でも女性の尻に敷かれることがあったのは興味深いですね!
Q8:中国歴代皇帝でも最大規模の後宮を持っていた隋の煬帝(ようだい)には、何人の妾がいたと伝えられているでしょう?
A:600人
B:6000人
C:30000人
D:60000人
【Q8正解】
D
【Q8解説】
・中国王朝の末代は、次の王朝に誇張されて悪く伝えられるため、実際に6万人も妾がいたかどうかは怪しい。
・一般的な皇帝は数百人程度、好色な皇帝で数千人程度だと伝えられている。
6万人はとんでもない人数で想像もつかないですね💦
憧れる男性の方はいらっしゃるでしょうか笑?
Q9:中国の同性愛文化について、正しい選択肢を1つ選んで下さい。
A:古代においては男色は一般的で、歴史書にまとまった記述が存在していた。
B:歴史書の記述の量で言えば、男性同士・女性同士、どちらの記述も同じくらい散見する。
C:戦争中の陣内において、女性だけでなく男色のサービスが提供されるのは一般的だった。
D:李白と杜甫など、仲がとても良い詩人同士は、友情以上の関係であったとされている。
【Q9正解】
A
【Q9解説】
・『史記』『漢書』の佞幸伝(ねいこうでん)では、歴代天子が寵愛した男妾が挙げられている。
→例えば董賢(とうけん)という男妾は、前漢の哀帝に愛されすぎて帝位を譲られかけている。
(中国社会において最も男色が広がったのは明代。)
・女性同士もあったが記述は少ない。
日本の男色は割と有名ですが、中国でも古くから男性同士の愛情が認められたのは意外かもしれませんね💡
Q10:古代中国における性愛文化について、正しい選択肢を1つ選んで下さい。
A:成人男性向けのセクシーな書籍が発見されている。
B:貴族の間で獣姦がたしなみとされた。
C:性行為によって健康を維持する考え方が流行した。
D:同性愛に加え、近親相姦も許容されていた。
【Q10正解】
C
【Q10解説】
・Cについて、「房中術」(ぼうちゅうじゅつ)と呼ばれるもので、特に貴族間で流行していた。
・Aについて、卑猥な書籍は発見されていないが、女性の墓から男性器の張型が出土している。
・Bについて、同性愛には寛容な一方、近親相姦や獣姦は社会的にタブー視されがちであった。
・Dについて、近親相姦は基本的にタブー視されていた。例えば、秦の時代の法律においては異父同母(異姓)の兄弟姉妹での近親相姦は死罪とされた。
性行為に健康維持のイメージを持つ現代人は少ないかもしれませんね笑💦
以上、中国の恋愛結婚・性愛にまつわる問題を出しましたがいかがだったでしょうか?
今回の問題を作成する際に参考にした書籍を紹介させてもらいます。興味があればどうぞ!
【参考文献】
・川合康三『中国の恋のうた』(岩波書店、2011年)
・柿沼陽平『古代中国の24時間』(中公新書、2021年)