ポイント
- 熟語の中には、差別的な歴史背景を持つものが存在している。そのような熟語については、しっかりと歴史・文化を学ぶ必要がある。
- 「未亡人」は「夫に先立たれて本来は後を追って死ぬべきなのに、まだ死んでいない妻」、「南蛮」は「南方にいる野蛮な人々」、「小説」は「価値のない説」が原義であり、本来はどれも差別的な意味合いを持っていた。
- 「未亡人」「小説」は儒教・朱子学の影響、「南蛮」は中華思想の影響を受けて成立している。
1、「旦那」は差別用語?
こんにちは。本日は、「熟語と差別」というテーマで学びを深めていきましょう。
こんにちは。前の授業で、「㉒外来語を漢字表記する際、字義を軽視(時に無視)して音によって固有名詞となったもの」を学んだ時、「旦那」は差別ではないか?みたいな話になりましたよね。
そうです。昔の夫婦関係は、「夫が稼ぎ、妻が家事を行う」のように、役割分担されていたからです。稼ぐ者→夫のように意味が変化し、旦那=夫のように定着しました。
結局、「旦那」って言葉は差別用語なんですか?性別によって役割を決めつけている!みたいな。
正直これは、「その人がどう思うのか?」「世論がどのように認識しているのか?」によって変わるので、簡単に白黒つけることはできません。
そんな曖昧な…💦
実際、私は旦那という熟語の背景を知っているので、あまり使わないようにはしていますが、背景を知らずに使っている人はいますね。
私も「旦那さん」とか使ったことあります。でも、使わないほうがよいのかな?💦
「使わないほうがよい」という意見も一理ありますが、「使う本人と相手が差別を意識していないなら問題ない」と意見にも一理あります。
2、「未亡人」はとてつもない男女差別の言葉?
しかし少なくとも、 「使わないほうがよい」という意見を主張したいのなら、1つだけでなく、より多くの熟語の意味について、歴史も含めてしっかりと学ぶ必要があると思います。(厳密に言うと熟語に限らず全ての言葉について、しっかりと知る必要があります)
どういうことですか?
それは、同じく差別的な意味を含んでいる「未亡人」「南蛮」「小説」という熟語の成立を知れば分かります。
まずは未亡人について学びましょう。未亡人ってどんな意味ですか?
えっと…「夫に先立たれた妻」って意味ですよね?小説とかで使われているのを見たことがあります。
正解です!では、「未亡人」を漢文として書き下してみましょう!
えっと…「未」は再読文字で、「未だ亡くならざる人」ですか?
さすがです!つまり、「未亡人」とは「夫に先立たれて本来は後を追って死ぬべきなのに、まだ死んでいない妻」という意味です。
えっ…💦?なんで夫が死んだら妻も死なないといけないんですか?💦
これには、儒教・朱子学の闇の部分が関係しています。朱子学とは、儒教の一派で、昔の中国の価値観に多大な影響を及ぼした教えです。
儒教というのは、女性に対し厳しい部分があります。特に女性の再婚は認めません。さらに、夫を追って自殺することが「節を守る」として賞賛・奨励されることがありました。
えぇ…気持ち悪い💦
現代の感覚からするとそうだと思います。しかし当時は国家がそれを奨励し、夫を追って自殺した妻を表彰することがありました。
頭がおかしい…💦
「未亡人」がいつの時代に成立したのかは分かりませんが、未亡人はこのような儒教や朱子学の影響があって成立した言葉です。
これまで知らずに使っていたけど、
…今後絶対に「未亡人」って言葉は使いません💦
中国における妻については、「なぜ論語は「善」なのに、儒教は「悪」なのか」という本の185p~198pにまとめられています。その他儒教についても分かりやすく学べるので、よかったらご覧になってみて下さい。
3、「南蛮」は中華思想に基づいた差別語
次に、「南蛮」という言葉も、元々は差別的な意味を持っています。
えっ!?私チキン南蛮とか南蛮漬けとか好きですけど…
「南蛮」とは元々、「中華思想=中国が最も優れており、それ以外の地域を劣っているという考え」が下敷きになっています。
具体的には、「北狄」「東夷」「南蛮」「西戎」などと呼ばれていました。そして、「狄」「夷」「蛮」「戎」は悪い意味です。
ちなみに、日本はかつて中国から「東夷」とみなされていました。
よく考えると、「蛮」って「野蛮」の「蛮」ですもんね…
そして、日本における「南蛮」とは、16世紀以降、ポルトガル人やスペイン人などの西洋人を指すようになり、西洋由来の物にも「南蛮」とつけられるようになりました。ここには、そこまで差別的な意味合いは無かったと思われます。
チキン南蛮は、西洋由来の唐辛子やネギなどを材料に作るため、「南蛮」とつけられたそうです。
知らなかった💦「南蛮」って言葉1つにも、日中文化がすごく影響しているんですね。
結局、「南蛮」って言葉は使わないほうが良いのでしょうか?
分かりませんが、スペイン人やポルトガル人がこのような歴史的背景を知れば、「使わないで欲しい」と主張する可能性はありますね。
難しいなぁ笑 でも先生が言った「言葉が差別的かどうかは、「その人がどう思うのか?」「世論がどのように認識しているのか?」によって変わる」と言った意味が少し分かりました。
4、現代ではありえない? 「小説」=「価値のない説」
また、「小説」という単語も、元々は「小なる説」、つまり「取るに足らない説」「価値のない説」というのが原義で、うわさやフィクションに関連する話を「小説」と称していました。
現代だと「小説」にさげすんだ意味ってないですが、元々はかなり悪い意味だったんですね💦
ちなみに、この「小説」は「大説」=「天下国家の政治のことを記した大いなる説」=四書五経に対する語でした。
世界をよくするのに使えそうな内容が評価されて、うわさやフィクションは「使えない」と評価されたんですね💦現代の小説家さんが聞いたら悲しむでしょうね💦
現代では小説に悪い意味はなく、むしろ、ライトノベルと比べ、高尚なイメージすらありますね。
フィクションもワクワクしたり知らない世界を知れたりと、役に立ちますよ!
その通りだと思います💡
今回紹介した熟語(「旦那」「未亡人」「南蛮」「小説」)は、どれも現代では差別的な意味合いを持って使っている人はいないと思いますが、原義を見てみるとあることは知っておくと良いですね。
どの熟語にも、中国の歴史的な文化を知れて面白かったです。ありがとうございました!
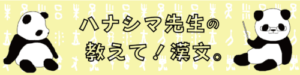
-01-940x627.png)

-03-160x160.png)
-01-160x160.png)