もくじ
ポイント
- 漢文における理想の妻として、①「夫に適確なアドバイスを行う賢い妻」、②「何があっても夫に忠節を捧げる妻」の2パターンに分けられる。
- 漢文におけるダメ妻の特徴として、「私利私欲を満たすために政治に口出しし、国を混乱させる妻」が挙げられる。
- 漢文(中国史)におけるダメ妻の特徴として、「私利私欲を満たすために政治に口出しし、国を混乱させる」という点が挙げられる。具体的には、妲己(だっき)、驪姫(りき)、呂太后(りょたいごう)が挙げられる。
こんにちは。本日は、中国における理想の妻とダメ妻について紹介します。これを知っていると、漢文で妻が出てきた際、話をある程度推測することができます💡
理想の妻…やっぱり、超絶美人とかですか?✨
もちろん、美しい女性はそれだけで評価されましたが、特に1、「夫に適確なアドバイスを行う賢い」妻や、2、「何があっても夫に忠節を捧げる」妻が賞賛されました。
「夫に適確なアドバイスを行う」「何があっても夫に忠節を捧げる」って、どんな嫁さんですか?
以下で具体的に取り上げます💡
1、夫に適確なアドバイスを行う 樊姫(はんき)・衛姫(えいき)
樊姫(はんき)(『列女伝』賢明伝より抄訳を掲載)
樊姫は、楚(そ)の荘王(そうおう)の妻である。荘王が即位したばかりのころ、趣味である狩りに熱中し、政務がおろそかになっていた。樊姫はこれでは良くないと思い、荘王に程々にするよう伝えた。
しかし荘王は、それらかも狩りに夢中であった。言葉では通じないと考えた樊姫は、鳥や獣の肉は食べないことによって、荘王へ抗議した。3年後、荘王は自身の過ちを改め、真面目に仕事を行うようになった。
また、かつて荘王が臣下の虞丘子(ぐきゅうし)という人物を賢者だと高く評価した。すると樊姫は笑って荘王にこう述べた。「虞丘子は確かに賢者かもしれませんが、忠義が足りません。」と。荘王は、なぜ虞丘子に忠義が足りないのか質問すると、「虞丘子は高い地位にありながら、自分の親族しか推薦しません。これは、だんな様のためにはなりません。また、もし虞丘子が賢者を知っていながらそれを推薦しないのなら不忠者ですし、そもそも賢者を知らないのであれば、自身も賢者ではありません。」と述べた。荘王は樊姫の言葉を聞くと納得して喜んだ。
後日、このことを虞丘子に伝えると、虞丘子は図星をつかれて恐縮し、何も答えることができなかった。その後虞丘子は、孫叔敖(そんしゅくごう)という人物を推薦し、孫叔敖の活躍により、荘王は覇者となった。
楚→国名。 覇者→諸侯をまとめるリーダーのような存在。
衛姫(えいき)(『列女伝』賢明伝より抄訳を掲載)
衛姫は、斉(せい)の桓公(かんこう)の妻である。桓公や覇者としての道を歩んでいる中、あるとき、諸侯が桓公のもとを訪れたが、衛(えい)という国だけは来なかった。桓公はこれを無礼として怒り、宰相である管仲(かんちゅう)と共に衛を攻撃する段取りを整えていた。
その後、桓公が衛姫と会った際、衛姫は「どうか衛の罪をゆるしていただけないでしょうか。」と桓公へお願いした。桓公は「私は気にしていない。」と嘘をついた。しかし衛姫は、「だんな様の険しい声色や荒だった顔色を観察する限り、衛を討伐なさろうとされていることが分かります。そこでお願い申し上げた次第です。」と述べた。桓公は、改めて衛を許すと約束した。
翌日、桓公が政務と取っている際、管仲が「殿の今日の様子は、とても心が落ち着かれているようです。衛を攻撃するというお気持ちは無くなられたようですね。」と述べた。桓公は「その通りだ。」と答えた。
その後桓公は、「衛姫と管仲がいれば、私がいくら愚かでも安心して覇者としてやっていける。」と述べた。
斉→国名。 衛→国名。 管仲→斉の名宰相
なるほど…たしかに樊姫と衛姫はどっちも夫をうまくサポートしてますね💡
てゆうか、衛姫さん賢すぎでは?夫の部下の問題点に気付くなんて💦
確かに、中々できることではないですね。また、衛姫のほうもすごいですよ。何せ、あの管仲(かんちゅう)と並んで評価されている訳ですから✨
管仲ってそんなに凄いんですか?
凄いですよ!中国史上、屈指の名宰相ということができます✨桓公は、その管仲と衛姫を同じくらい評価しています。
なるほど…でも、衛姫って、顔色やしぐさから桓公の真意を見抜いて、戦争を止めただけだから、衛姫と比べるとインパクトが足りないなぁ💦
そもそも、なぜ衛姫は戦争を止めさせたのだと思いますか?
戦争がいけないことだから?
確かに、むやみに戦争を起こすのは良くないとされていましたが、恐らく別の理由もありました。それは、「覇者である夫が、些細な理由でも許さないという態度を取れば、諸侯から覇者としての器がないとみなされ、求心力を失うことを危惧したから」です。
それが本当なら、衛姫も樊姫に負けないくらい夫をサポートできていますね!💡
2、何があっても夫に忠節を捧げる 宋人(そうひと)の女(むすめ)・息(そく)の夫人
次に、あと一つの理想の妻像である「何があっても夫に忠節を捧げる」妻について紹介します。
宋人(そうひと)の女(むすめ)(『列女伝』貞順篇より抄訳を掲載)
宋(そう)という国の出身の娘は、蔡(さい)という国のとある家に嫁いだが、夫が悪い病気にかかった。そこで娘の母は、娘を離婚させて別の家へ嫁がせようとした。
すると娘は、「夫の不幸は私の不幸でもあります。また、夫に過失があったわけでも、夫が私と離婚したいと言っている訳ではありません。従って、別れることなどできません。」と答えて離婚を拒み、ついに母の言いつけを聴き入れなかった。
息(そく)の夫人(『列女伝』貞順篇より抄訳を掲載)
息という国は、楚という国に滅ぼされた。息の君主の夫人は、楚王から妻として迎えられた。その後、夫人は夫に対し、「私は絶対に再婚しません。別れて生きるよりは、死んで一緒にるほうがましです。」と述べた。
夫は夫人の自殺を止めようとしたが、結局夫人は自殺してしまった。夫は後を追って自殺した。楚王は、その夫人が貞節を守ったことを称え、夫と共に丁重に弔った。
宋人の娘は、夫が病気でも離婚しようとせず、息の夫人は夫が一国の主でなくなっても離婚しようとしなかった。確かに、「何があっても夫に忠節を捧げる」ですね💦
今更なんですが、「忠節」ってどんな意味ですか?
「忠節」とは、ここでは「自分の都合ではなく夫第一で物事を行う」というニュアンスが強いです。
なるほど…理屈は分かりますし、忠節が立派なのも何となくわかりますが、正直、彼女たちはこれで幸せなのか?って思っちゃいます。
だって、宋人の娘は、元気な男と再婚したほうが絶対楽ですし、息の夫人も、楚王との再婚を認めれば、前までと変わらない優雅な生活ができていたでしょうし…
確かに、彼女たちが幸せだったのかどうかは分かりません。しかし少なくとも、中々できる選択ではありませんし、これが伝統的な理想の女性として称えられていたのは確かです。
私としては、彼女たち自身の幸せを第1に生きて欲しいって思っちゃいます💦
そうですね…私もこの価値観を見ると、どうしてもモヤモヤしてしまいます。
ちなみに、当時、妻の再婚は良くないものだとされていましたが、夫の再婚は容認されていました。
それめっちゃ不平等じゃないですか💢?
そうですね。今と比べると、中国は伝統的に男尊女卑的な側面があります💦まぁ色々理由はあるんですけどね。
現代日本だと、このようなことを妻が求められることがあまりないですし、男女平等ってよく言われるので、私は良い時代に生まれたのかもしれません。
そうかもしれません。一方で、昔の中国にはなかった妻の責任や苦労もあるので、一概には言えませんね💦とにかく、漢文で妻がでてきた際は、このような価値観を頭に入れておくと、戸惑わずに解けるでしょう✨お疲れ様でした!
3、漢文におけるダメ妻の特徴とは?
次に、理想とは真逆のダメ妻について紹介します。
ざっくりと言うと、理想の妻像とは真逆の人がダメ妻です。
えっと…夫に良いアドバイスができず、裏切ったりする妻ですか?
アドバイスどころか、夫の足を大きく引っ張ることが多いです。さらに、美人の場合が多いです。
外見だけ良くて夫に愛されているけど、自分勝手に振る舞って国を混乱させる妻ってことですね。
その通りです。今でも社長やスポーツ選手の妻はだいたい美人ですが、たまに夫の仕事に口出しして業績や成績を悪化させてしまう場合がありますね。あれと少し似ています。
あー…たまにそういう人見る気がします。いわゆる「さげまん」というやつでしょうか。
今も昔もダメな妻は変わらないみたいですね笑
そうみたいですね。それでは、ダメ妻の具体例として3人紹介したいと思います✨
4、残虐な刑罰を考案した美人妻 妲己(だっき)
まず取り上げたいのは、妲己(だっき)です。
タイトルがめっちゃ不穏なんですが…笑
妲己は周王朝の紂王(ちゅうおう)という人物の妻でした。非常に美しかったとされます。
美人セレブ妻ですね✨
しかし、妲己は紂王が仕事を怠るのを注意するどころか、一緒に豪勢に遊びます。
例えば、酒を流して池を作り、木々に肉を吊して林を作り、人々を裸にさせて昼夜問わず酒を飲み続けました。
酒の池に肉の林って、とんでもない贅沢ですね。いくらかかるんでしょう?
いくらかは分かりませんが、自分たちの金をこんな風に使われて、民衆は紂王と妲己を恨んだようです。
それはそうでしょうね笑。現代でも政治家の税金の使い方は厳しく監視されていますし。
ちなみに、ここから「酒池肉林(しゅちにくりん)」という熟語が生まれ、「贅沢の限りを尽くすこと」という意味で今でも用いられます💡
言われてみれば、「酒池肉林」ってまんまですね笑 この言葉は、妲己と紂王が生んだ言葉だったんですね💡
2人がこのような振る舞いを行ったいたので、部下が意見したり反乱を起こすことがありました。妲己はそのような人々を罰する方法として、「炮烙(ほうらく)の刑」を考案します。
「炮烙(ほうらく)の刑」 ってどんな刑罰なんですか?
諸説ありますが、『列女伝(れつじょでん)』という文献によれば、銅の柱に油を塗り、下から熱させ、その上を罪人に渡らせたと言います。油が敷いてあるので、当然罪人は柱から落ち、焼けただれたそうです。
えぇ…なんかアトラクションっぽいけど、めちゃくちゃ残忍ですね💦
また妲己は、その落ちて焼け苦しんでいる罪人を見て、笑っていたそうです。
えぇ…さらにドン引きです💦道徳心のかけらもない!!
結局、紂王は部下からの反乱を抑えきれず、自殺します。妲己は捕らえられて、断首されました。
まぁ当然の結果って感じですね。しかし、妲己が悪いっていうか、紂王と妲己の2人が悪いって感じですね💡
そうですね。漢文において、紂王はダメ君主の代名詞、妲己はダメ妻の代名詞として登場することがあります。知名度が高いので、知っておいて損はないでしょう。
5、跡継ぎ問題を起こして国を混乱させた美人妻 驪姫(りき)
次に紹介するのが驪姫(りき)です。彼女は、春秋時代、晋(しん)の献公(けんこう)という殿さまの妻です。
タイトルから見るに、この人も大分やらかしてそうですね…💦
驪姫は、美しい女性であり、献公にとても愛され、献公の子どもを産みます。一方、その子どもより前に生まれた別の妻の子が跡継ぎとして既に決まっていました。さてマオさん。驪姫は何をしたと思いますか?
これって、前勉強した竇皇后(とうこうごう)と同じことしたんじゃないですか?つまり、その跡継ぎ予定の子どもを殺して…
その通りです。中国の政治あるあるが大分分かってきましたね✨
驪姫は、跡継ぎ候補はもちろん、その他に候補になりそうな子どもを次々と始末します。この方法が非常に狡猾(こうかつ)でした。
狡猾って、ずる賢いってことですよね?何したんですか?
例えば、ある息子が亡くなった母を祭る際、捧げる供物を用意し、献公に届けました。しかし献公は不在だったので、代わりに驪姫が受け取ります。
そして、その受け取った供物に対し、強力な毒を仕込み、「その人が献公を毒殺しようとしている!」と主張します。そのでっち上げた事件のせいで、その供物を用意した息子は自殺します。
思った10倍くらい狡猾でした…💦
その後、驪姫は念願であった自分の息子を跡継ぎにすることに成功しますが、献公が亡くなった後、臣下に国家を混乱させたとして殺されます。
痛々しいけど当然の結果というべきでしょうか…
このように、政治介入して自分勝手に振る舞って混乱させるのは、割とポピュラーなダメ妻です。割と登場するので、知っておくと良いでしょう。
現代だと、安○元首相の夫人が割と似ている気がしますね。
あー確かに、驪姫ほどではないですが、明らかに夫の足を引っ張っていましたしね💦あのイメージとある程度重なるかもしれません。
6、夫の国を乗っ取ろうとした妻 呂太后(りょたいごう)
最後に、呂太后(りょたいごう)という人物を紹介させて下さい。
今回もタイトルが不穏だぁ…💦
呂太后は、前漢の初代皇帝、劉邦(りゅうほう)の妻であり、2代目恵帝(けいてい)の母親です。
ざっくり言うと、呂太后のしたことは、驪姫の成功バージョンと言って良いと思います。
呂太后も、自分の息子を跡継ぎにするために色々したんですか?
頑張りましたが、驪姫のように汚いことを行わなかったです。臣下の反乱を未然に報告するなど、国のために働き、発言力を高めます。だからかもしれませんが、呂太后は無事、息子を後継者に据えることができました。
おー✨驪姫よりすごくやり手ってことですね!
そうですね。元々、夫の劉邦は、呂太后の息子=恵帝の穏和な性格を嫌っており、何度も後継者から外そうとしたり、他の後継者を立てようとしていました。それを呂太后がうまく工作し、恵帝が後継者となりました。
問題は、劉邦が死んでからです。まず、別の美しい夫人とその息子を殺します。
正体表しましたね💦
特にその殺し方が残忍でした。呂太后は夫人が晩年、劉邦に愛されたのが気に入らなかったようで、両手両足を切り、目をくりぬき、耳と喉を潰し、便所に放り込みました。呂太后は、その様子を見て笑っていたそうです。
えぇ…ドン引きです…
また、その後、呂太后は自身で政治を取り仕切るようになり、自分の一族を要職に就け、やりたい放題します。
驪姫はうまくできなかったけど、呂太后はうまくやりましたね!
そうですね。しかし間もなく呂太后は亡くなり、その後一族は全員殺されます。
あぁ…悪いことはするもんじゃないですね💦
以上の部分は、横山光輝『史記』で漫画として読むことができるので、読んでみて下さい。面白いですよ。
また、呂太后は、則天武后(そくてんぶこう)・西太后(せいたいごう)と共に「中国三大悪女」と呼ばれることがあります。
則天武后と西太后は世界史で聞いたことがあります。この2人の話もいつか聞いてみたいなぁ…
機会があればまた紹介しますね。本日もお疲れ様でした!
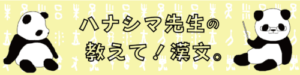
-19-940x627.jpg)

-03-160x160.png)
-01-160x160.png)